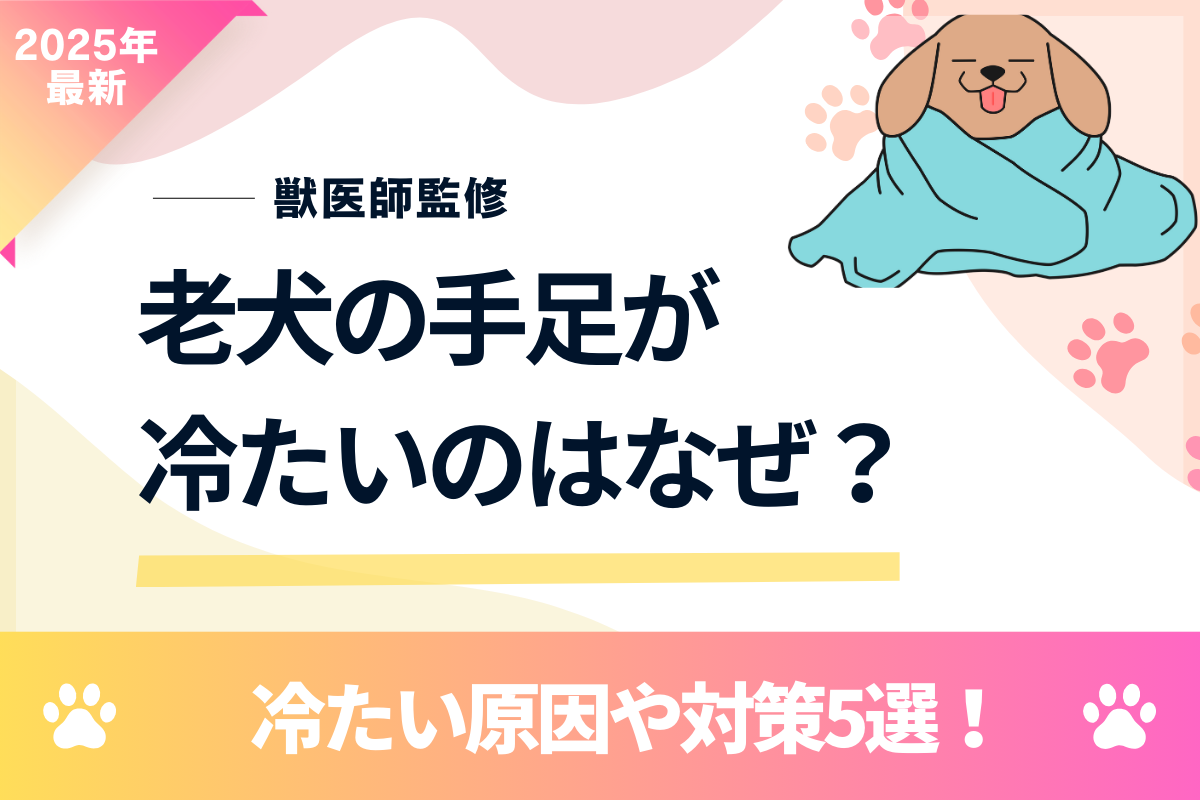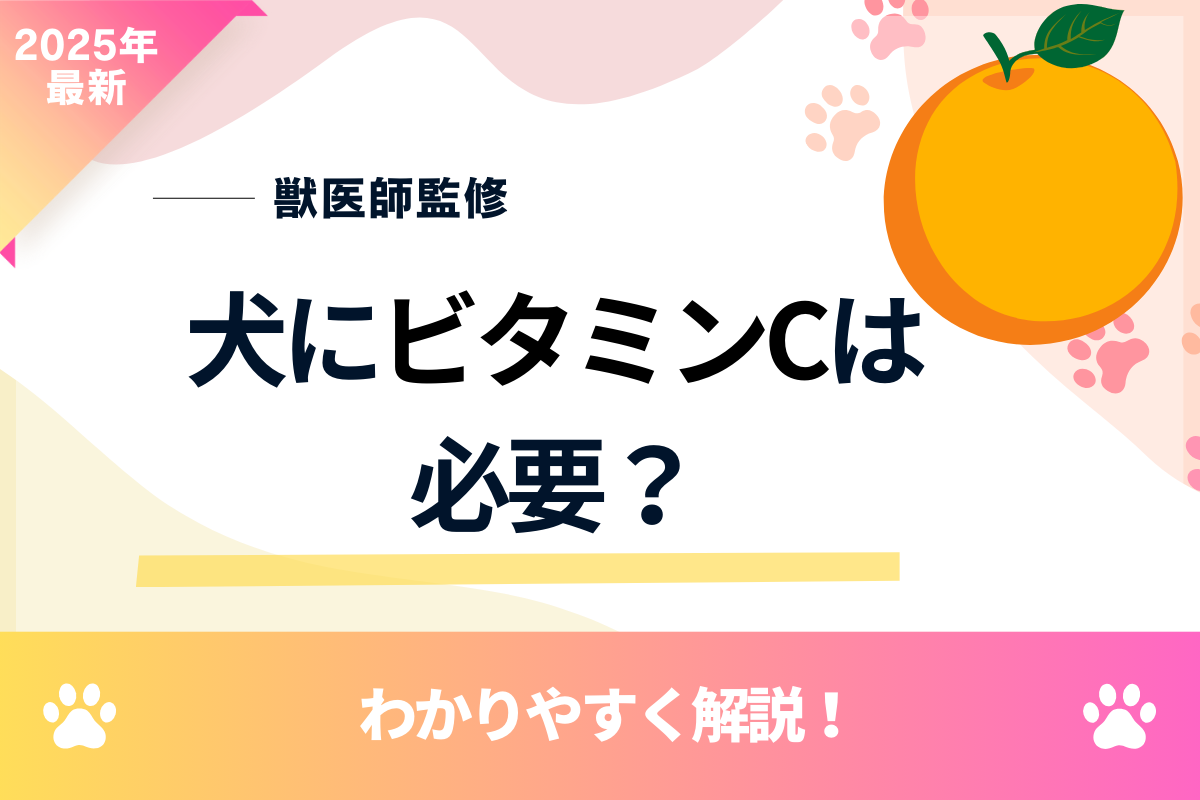シニア期を迎えた愛犬の手足が冷たく感じられると、「もしかして病気ではないか」「冷えが原因で体に負担をかけていないか」など、飼い主としては様々な不安が募ります。実際に、加齢による体温調節機能の低下や血行不良、犬種特有の特徴など、老犬の手足が冷える原因は多岐にわたります。そして、この冷えを見過ごしていると、免疫力の低下や体調不良につながる可能性も否めません。本記事では、老犬の手足が冷える具体的な理由から、日常の工夫で簡単に取り入れられる冷え対策まで、幅広く解説していきます。愛犬と長く健康に暮らすために必要なポイントをしっかり押さえて、冷えの悩みを解消していきましょう。
- 老犬の手足が冷たくなる原因
- 体が冷えることによるリスク
- 冷やさないための対策について
目次
老犬の手足が冷たくなりやすい理由とは?
老犬になると、若い頃と比べて体温調節の機能が低下しやすくなります。
犬の体内でも加齢によって血管がやや細くなったり、血流を制御する力が弱まったりすることが大きな要因です。そのため、手足を通る血液の量が十分に行き渡らず、末端部分が冷たく感じられることがあります。
また、高齢になると筋肉量が落ちていくため、筋肉が生む熱が以前ほど体を温められなくなります。こうした要因の積み重ねが「手足が冷える」という症状が起きております。もちろん、冷えが必ずしも重い病気の兆候とは限りませんが、飼い主の方が愛犬の状態を見極め、必要に応じて早めの対策をとることは非常に大切です。
ここからは、「生活習慣」「犬種」などの観点から原因を深堀りし、解説しておりますので、老犬の冷え対策を行う際の参考にしてみてください。
生活習慣による原因
老犬になって活動量が減少すると、筋肉や関節を動かす機会が少なくなるため、血流が滞りやすくなります。若い頃は走り回っていた犬でも、シニア期に差し掛かると散歩の時間が短くなったり、すぐに疲れて休んでしまうことも多いです。運動不足による血行不良は手足の冷えを招きやすいだけでなく、肥満や関節への負荷増大などのリスクを伴います。
また、食生活の面でも、老犬は消化機能が低下したり、歯や顎の力が衰えたりする影響で、柔らかい食べ物や飲み込みやすい食べ物が中心となり、栄養バランスが崩れやすくなります。
体を温めるエネルギーが不足すると、末端の手足の温度が低下しがちです。例えば、栄養が偏ったまま無理にダイエットをさせている場合、体脂肪とともに筋肉量も落ちてしまい、結果的に体を温める機能がさらに損なわれるケースも考えられます。こうした生活習慣を見直すことは、冷え対策の基本となります。
犬種による場合
犬種によっては被毛が薄かったり、体格が小さかったりするため、外気温の影響を受けやすいものがあります。例えば、チワワやミニチュアダックスフンドなどの小型犬は、体積に対して体表面積が大きく、放熱が早く進むことから手足の冷えを感じやすい傾向にあります。
また、以下の犬種は被毛による保温効果が限定的なため、体温を維持しづらいとされています。
| 短毛種 | シングルコート |
|---|---|
| グレート・デーン | プードル |
| ボクサー | マルチーズ |
| ダルメシアン | ヨークシャー・テリア |
| ドーベルマン・ピンシャー | イタリアン・グレーハウンド |
| フレンチ・ブルドッグ | チャイニーズ・クレステッド |
もともと寒冷地に適応している犬種でも、老化による体力低下や血流量の減少が加わると、十分に手足を温められなくなる場合があります。こうした犬種特有の性質と、加齢による体温調節機能の衰えが重なることで、冷えが進んでしまうのです。飼い主の方は愛犬の犬種の特徴をよく理解し、老化が進む前から適切な寒さ対策を行いましょう。
老犬の手足が冷たいとどうなる?
老犬の手足が冷たい状態を放置していると、血行不良によって体全体に行き渡る栄養や酸素の量が減り、免疫力の低下を招きやすくなります。特に老犬は若い頃に比べて基礎代謝が落ち、体温を保つためのエネルギーを多く消耗しやすい体質となります。
例えば、体がだるそうに見えたり、かかとや関節周りをかばうような仕草を見かけた事はありませんでしょうか?もしかすると、「冷え」が体の負担となっている可能性があります。
こうした状態が続くと、犬自身が動きたがらない、寝ている時間がさらに長くなるなど、充実した生活の妨げとなる可能性も考えられます。
さらに、冷えが長引くと関節周辺の血流が悪くなり、動きがぎこちなくなったり、階段を嫌がったりといった行動の変化が見られることがあります。老犬の場合、血管や関節に負担がかかりやすく、一度不調に陥ると回復に時間を要するケースが多いです。軽度の冷えならば、室温や湿度の管理を見直すなどの日常ケアで改善できる場合も少なくありませんが、極端に手足が冷たい状態やふらつき、食欲の低下といった症状が重なる場合は、疾患が隠れている可能性を考慮する必要があります。飼い主が早めに冷えの兆候を感じとり、早めの対策を行いましょう。
冷え性が原因で病気となるリスクも
「冷え性」による、血行不良や免疫力低下から病気などへ発展してしまう可能性があります。
老犬が長期間、冷えている状態が続くと、血行不良が原因で各部位への負担が蓄積しやすくなります。
「冷え性」が直接的に病気に関わる訳ではありませんが、間接的に関わる恐れがあり、実際にどのような影響があるのかを見ていきましょう。
▼以下は、老犬の冷え性が関係して発症・悪化する恐れのある病気の例
| 関節炎・変形性関節症(骨関節疾患) | 老犬は関節が弱っていることが多く、冷えによる血行不良で関節周りの筋肉や靭帯が硬くなり、痛みが生じやすくなります。 炎症が進むと、歩行や起き上がり動作が困難になる場合があります。 |
|---|---|
| 心臓疾患・循環器系の影響 | 血行不良が続くことで、心臓や血管に負担がかかりやすくなります。特に心臓に持病を抱えている老犬は、冷えによる血圧変動や心拍数の乱れが症状を進行させるリスクを高めます。 |
| 呼吸器系への影響 |
冷えによって体力が低下し、免疫力が落ちることで、呼吸器系の感染症や持病(気管虚脱や気管支炎など)が悪化しやすくなることがあります。特に空気が乾燥しやすい冬場は、冷えと合わせて呼吸器への負担が大きくなりやすい。 |
| 内臓機能の低下(肝臓・腎臓など) | 血行不良が長期化すると、腎臓や肝臓の機能も影響を受ける場合があります。老犬はもともと内臓の働きが弱っていることが多いため、冷えが引き金となって代謝がさらに落ち、持病の悪化や新たな不調の原因にもなる。 |
| 皮膚トラブル(皮膚炎・脱毛など) | 冷えによる新陳代謝の低下は、皮膚のターンオーバーに影響を与えることがあります。血行不良で必要な栄養が行き渡りづらくなると、炎症や乾燥、脱毛のリスクが高まります。 |
上記のように、冷え性自体が“直接”病気を作り出すというより、体の各所への負担を増大させ、持病などを悪化させる要因になるケースが多いです。
老犬の手足が冷えていると感じた際には、早めに保温対策や生活習慣の改善を行い、必要に応じて獣医師に相談することが大切です。
【放置厳禁】冷え対策5選!
老犬の手足の冷えを防ぎ、体の状態を安定させるには、日常のケアや生活環境の整備が欠かせません。
特に老犬の場合は、体温を保持しにくいため、冷えやすい環境に長くいると体が冷え切ってしまうことがあります。冷え対策を行うことで、体温調節機能を補い、適切な体温を維持しやすくなります。
また、冬場などで、運動直後だった場合に冷えた場所で休ませておくと、犬自身がストレスを感じる原因にもなります。
犬が快適に過ごせる環境を整える上でも、飼い主の方は冷え対策をいくつか知っておく必要があります。
ここでは、取り入れやすい5つの方法をご紹介します。それぞれの対策を組み合わせながら、愛犬に合った形で実践してみてください。
室内の温度調整を管理しよう
老犬が快適に過ごせる環境をつくるためには、室内温度や湿度の管理が重要です。気温差が激しいと体が冷えやすくなるうえ、高齢犬は温度変化に適応しづらいと言われています。
例えば、冬場だけでなく冷房を多用する夏場でも、エアコンの効きすぎた部屋で犬が冷えすぎてしまうことがあります。犬は人間より、2~3度ほど対応が低いため、人間が肌寒く感じている時に犬は体感もっと寒さを感じています。特に、老犬の場合は、休息時間が長い場合が多いため、床の冷たい場所やエアコンの風が直接当たる場所などを避けて、犬が自分で快適な位置を選べるようにしておくと安心です。
部屋に温度計や湿度計を設置し、エアコンや加湿器だけでなく、床暖房や犬用ベッド・毛布などで温度調整を行うなどの冷え対策を行いましょう。
適度な運動をさせよう
老犬でも無理のない範囲で定期的な運動を行うと、血行促進や筋力維持が期待できます。
筋肉は体を温めるうえで重要な役割となり、適度に動かしてあげることで衰えを遅らせることができます。
例えば、散歩コースを1キロ以内で短めに設定して、1日に2,3回に分けて行う方法や、室内でも歩行練習を取り入れるなど、愛犬のペースに合わせた運動方法を探してみましょう。
逆に急に長時間散歩させたり、無理に走らせた場合、関節や心臓に大きな負担がかかってしまい、疲れから体調を崩す恐れもあります。無理ない運動を行うように心掛けましょう。
食生活を見直そう
老犬は若い頃と同じ食事をしていると、カロリー過多や塩分過多になりやすく、栄養不足を起こす可能性もあります。特に体を温める作用のあるたんぱく質や、血流を促進するビタミンE、鉄分などの栄養素が不足すると、冷えが進行しやすくなります。
対策としては、スープ状の食事や、温めてから与えるごはんなど、体に優しく消化しやすい食べ物を与えるようにしましょう。他にも、ドッグフードを少し温めてあげたり、冷たい水ではなく、白湯にするなどの簡単な工夫でも効果的です。
しかし、持病を抱えている老犬の場合は、特定の食材を避ける必要があるため、注意する必要があります。
もし食材選びや与える量に不安がある場合は、動物病院で血液検査や栄養指導を受け、愛犬に適した食生活を見つけましょう。
足湯で温めよう
足湯は、老犬の手足を直接温める効果的な方法です。特に冬場や雨天続きで散歩不足の場合、定期的に足湯を行うことで血行を改善する事ができます。ぬるめのお湯に短時間だけ浸けるだけでも、血流が促進されやすくなります。
お湯の温度は37~38度程度で、夏場の場合は少し下げた34〜35度あたりで設定しましょう。
感覚としては、人間が少しぬるいと感じる温度が目安となります。
また、お湯から出た後に放置すると足が冷えてしまうため、足湯の後はタオルでしっかり拭き取ってあげましょう。
他の対策に比べ、短時間で温める事ができるため、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
マッサージをしよう
老犬の関節や筋肉は、加齢によって硬くなりやすい特徴があります。軽いマッサージで手足をほぐしてあげると血行が良くなる他に、リラックス効果も期待できます。
特に足裏や関節まわりを優しく撫でるように触れてあげると、末端まで温まりやすくなります。
血流が良くなることで不要な老廃物を排出し、むくみを取る効果もあります。
また、ご自宅でマッサージを行う他にも、近年では、犬にマッサージを実施してくれるドッグマッサージのサービスを提供しているお店も増えてきております。自分でマッサージを行う事に不安を感じられる方などで、もし興味がある方は愛犬を連れて行かれてはいかがでしょうか。
マッサージを通じて、飼い主さんが愛犬の体全体をチェックする習慣をつけると、しこりやイボなどの小さな変化にも気づきやすくなり、早期受診につなげられるメリットもあります。
心配な場合は動物病院での診察をおすすめ!
手足の冷えが長引いたり、ほかの症状(ふらつき、息切れ、食欲不振など)が合わせて見られたりする場合は、動物病院での診察を検討してください。老犬は若い犬よりもさまざまな病気にかかりやすく、放置すると症状が進んでしまうことがあるため、早めの対応が重要です。
診察時には、いつごろから手足の冷えを感じるようになったのか、どんな生活環境で過ごしているか、運動や食事の状況、体調の変化などをできるだけ詳しく伝えましょう。これらの情報が多いほど、獣医師は正確な判断がしやすくなります。費用や治療方法に不安があれば、事前にリストアップして相談するのも良い方法です。老犬の手足が冷たい場合、早めに専門家のアドバイスを受ければ、適切なケアや治療で快適なシニアライフをサポートすることが可能です。
犬に長く健康でいてほしいならサプリメントがおすすめ
手軽に愛犬の健康を簡単にサポートしたい方には犬用のサプリメントをおすすめします。
犬用のサプリメントでも様々な種類がありますが、「良質なサプリメントを与えたい!」という方に特におすすめなのが、WONDERFULです。
姫マツタケを原料とした溶けやすい顆粒状のサプリメントで、免疫力向上に優れ、動物病院でも使用されている安全性の高いサプリメントで、はじめての方でも安心して与えることができます。
おすすめの理由その①
殆ど流通していない高級キノコ「姫マツタケ」を贅沢に使用。
「姫マツタケ」は希少性が高く、免疫力向上の効果があり、
抗腫瘍作用、免疫賦活作用、肝臓や腎臓の機能改善や関節痛の炎症軽減などの多くの改善効果が見込める。
おすすめの理由その②
獣医院でも取り扱われている信頼性抜群のサプリメント。
βグルカン(免疫力向上)や核酸/RNA(疲労回復効果)など高級サプリに相応しい成分配合から、病院でも使用されている信頼性の高いサプリメントです。
また、不純物が一切含まれておらずオーガニック由来の姫マツタケ成分とデキストリンのみを使用。
中でも、姫マツタケエキスの成分比率が約70%を占めており、一般のサプリメンと比較しても圧倒的な品質を誇る高級サプリメントです。
仕事で忙しい方などは犬の健康をサポートしたくても時間がなく、一手間かけることも難しいのではないでしょうか?
WONDERFULはドッグフードなどに混ぜて与えるだけ!多忙なあなたでも簡単に愛犬の健康維持をサポートすることが可能です。